ウィーン・フィルとともに
ワルター・バリリ回想録
ワルター・バリリ著 岡本和子訳
音楽之友社
ISBN978-4-276-21793-5
ワルター・バリリと言えば、名門ウィーン・フィルのコンマスとして良く知られていますが、52歳のときに右ひじの故障から現役を引退、その後は教育者としての道を歩みます。
2001年には日本で弦楽四重奏のレッスンを行いTVでも放映されました。確かベートーヴェンの弦楽四重奏曲作品18-4だったと思うのですが、受講したクァルテットのメンバーに、16分音符がきちんと聴衆に聴こえるテンポで弾きなさいと、速過ぎるテンポを注意していたのが印象的でした。
実際、バリリ四重奏団の演奏はどれも落ち着いていて、ニュアンスに富んだ味わい深い演奏です。また、技術的なことでは、できるだけシンプルなフィンガリングを使うようにと1stヴァイオリン奏者に指摘していました。
「ファースト・ポジションで弾けるのなら、なぜそれで弾かないのですか?」と彼は言っていました。これは、音のクリアさや音程の安定感が失われるのなら、無理せずに下のポジションを積極的に使えということだったと思います。
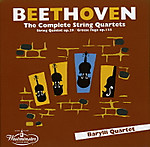 1938年、ワルター・バリリは17歳の若さでウィーン国立歌劇場管弦楽団およびウィーン・フィルに入団、翌年から両団のコンマスを務めました。また、1945年からは「バリリ四重奏団」を結成。数々の室内楽の名演を録音いたしました。なかでもベートーヴェンの弦楽四重奏曲全集(UCCW-1007)は名盤として誉れ高いものですね。現在でも格調高い名演としてその素晴らしさは語り継がれています。
1938年、ワルター・バリリは17歳の若さでウィーン国立歌劇場管弦楽団およびウィーン・フィルに入団、翌年から両団のコンマスを務めました。また、1945年からは「バリリ四重奏団」を結成。数々の室内楽の名演を録音いたしました。なかでもベートーヴェンの弦楽四重奏曲全集(UCCW-1007)は名盤として誉れ高いものですね。現在でも格調高い名演としてその素晴らしさは語り継がれています。
 また、ソロとしてもモーツァルトのソナタ集(UCCW-1007)、弦楽四重奏曲集、協奏交響曲、バッハの協奏曲等の名盤を残しました。
また、ソロとしてもモーツァルトのソナタ集(UCCW-1007)、弦楽四重奏曲集、協奏交響曲、バッハの協奏曲等の名盤を残しました。
これまたノーブルな名演の数々です。
演奏家として、コンサートマスターとしての卓越した技量を証明するエピソードが本の中に書かれていましたので、それを引用いたします。
コンサートマスター就任早々、力量を試される場となったのが、リヒャルト・シュトラウスの《町人貴族》組曲のレコーディングだった。この作品の中で弾かれる「仕立て屋の踊り」には、重音奏法での跳躍など、超絶技巧を要するヴァイオリン・ソロが多い。また当時の録音技術は今ほど成熟しておらず、1940年代にはまだテープをカットして編集することができなかった。このときの録音の指揮者はクレメンス・クラウスだったが、よりによって「仕立て屋の踊り」のところでオーケストラは何度も小さなミスを犯し、わたしはソロを何回も繰り返し弾く羽目にあった。
「あんたも一度くらい音を外したらどうかね?」とクラウスは冗談口調で言ったが、わたしは「すみません。このようにしか弾けないのです」と答えた。
すると首席ヴィオラ奏者で名教師としても知られるモラヴェッツ教授がすかさず、「このバリリって奴は尋常じゃない左手のテクニックの持ち主で、何でもすんなり弾けてしまうんですよ」と指揮者にむかって言ったという想い出話がある。
このように卓越した技術を持ちながら、決して鋭角的な演奏にならないのが、ワルター・バリリの凄いところだと思います。モーツァルトなど、実にさりげなく弾いているのですが、それを他の者が真似するのは非常に難しいでしょうね。
この本で私が最も注目した箇所は彼の使用楽器について本の中で触れられていたこと。こういった弦楽器奏者の著書では、楽器についても語られていることが少なくなく、そういった箇所を発見するのはこの上もない喜びでもあります。
その部分を引用しておきます。

わたしの愛する楽器について少し話をしておくべきだろう。芸術家としての人生をずっと共 に歩んでくれた彼女はフランス生まれで、1830年にパリでジャン・バプティスト・ヴィヨームによって製作された。そして1940年、ウィーンの有名なヴァイオリン製作者カール・カルテンブルンナーの店でわたしは彼女を手に入れた。
(左写真の楽器)
ということは、ウェストミンスターの録音等で聴けるワルター・バリリの演奏は皆このヴァイオリンで演奏しているということなのです。
この本の表紙の写真からも、うっすらですが楽器の象嵌細工がダブル・パーフリングであることが確認できますね。表紙のヴァイオリンもこのヴィヨームに違いありません。
これまで、バリリがヴァイオリンを持っている写真というものを私は見たことがなかったので気付きませんでしたが、ヴィヨームだったというのは初耳で少なからず驚きました。ヴィヨームでもストラドやデルジェスのコピーではなく、マッジーニのコピーですね。確か松山冴花が使用しているヴァイオリンもこのマッジーニコピーだったと思います。
上記のモーツァルトのソナタやバリリ四重奏団の録音で聴くことができる、あの暖かい気品あるバリリのヴァイオリンの音色は意外にもこのフランスの名器、ヴィヨームのものだったのかと、今回改めてCDを聴き直して感慨深く思いました。

 045-989-1599
045-989-1599